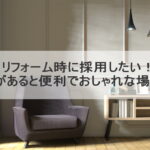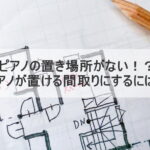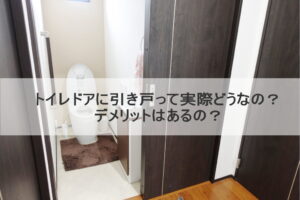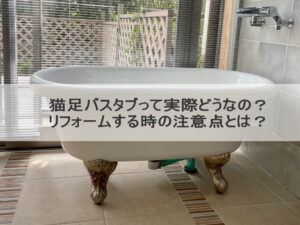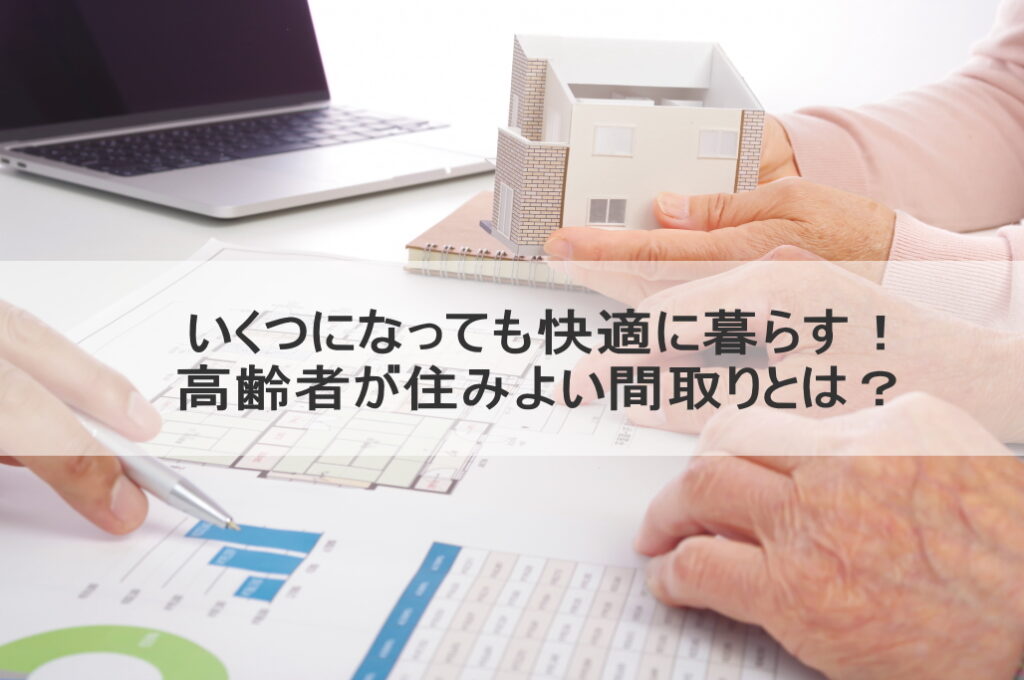
子ども達が巣立ち、家のリフォームのタイミングで今後歳をとった時のことを考えたり、高齢や病気になった親族と共にすむようになったりして、バリアフリーの家にリフォームする方は少なくありません。人生100年時代構想を政府が政策しているとはいえ、いくつになっても、快適に元気に暮らし続けるためには、まずは生活の拠点である家の状態や間取りが大きく影響します。そのためバリアフリーリフォームや間取りの変更は慎重に検討する必要があります。
高齢者が住みやすい家とはどんな家なのでしょうか?バリアフリーリフォームの失敗例から学び、さらに、いくつになっても快適に住み続ける家にするためのアイディアをご紹介したいと思います。
1. バリアフリーがバリアになる!?
高齢者が住みやすい家にするためにバリアフリーを意識する方は多いですが、良かれと思って行ったリフォームが、むしろバリアを作り出していることもあります。失敗例やバリアフリーの落とし穴について、プロ目線でご紹介したいと思います。
■段差を無くしすぎて足腰が弱った!
バリアフリーリフォームの定番といえば段差を無くすことですが、あまりにも段差を無くしてしまったことが、足腰を弱らせる原因になることがあります。
足を引っ掛けてしまうような扉のレールなどは無くしてフラットにすることで転倒を防ぎ、安全性を確保出来ますが、歩行に問題がないのであれば、あえて段差を無くすよりも手すりを付けて自分の力で上り下りできるようにしていた方が足腰の筋力を低下させずにすんだと感じている方は少なくありません。車椅子生活になった場合には段差が妨げになりますが、今出来ていることを早い段階から無くしてしまうと筋力の低下に繋がってしまうので、残存能力を使うことを意識しておくことは大切です。
また、大きな段差がある部分ではスロープを設けることも出来ますが、段差が高い場合は緩やかなスロープにするために距離をとる必要が出てしまいます。リフォームの場合、十分なスペースを確保することが難しい場合もあります。スロープにするよりも、段数を増やして緩やかに上れるようにするだけでも負担を減らし安全に上り下りすることができます。特に、体のバランスを崩しやすい片麻痺の方や、パーキンソン病によってすくみ足になっている方にとっては、下りのスロープは、体が突進し転倒する可能性があるため、スロープよりも階段の方が安全な場合もあります。
体力や持病による体の状態、進行具合などは人それぞれなので、バリアフリー=段差を無くすこと、ではなく住む人の年齢や体力に合わせてバリアを無くすことを意識しましょう。
■独立性を確保するつもりが孤立に繋がった!
高齢になった親を家に呼んで二世帯で住む場合、プライバシーを守ったり、出来ることを自分達でやってもらったりする独立性を意識しすぎて、孤立した暮らし、家や部屋に引きこもる生活になり、元気が無くなったという失敗例があります。
例えば、音漏れを気にして部屋を孤立したところに設けたことで、同じ家に住んでいるにも関わらず起きているか寝ているか分からない、顔を合わせない日がある、ということもあります。離れて暮らしていた時の方が定期的に行き来して顔を合わせ、コミュニケーションもとれていた、と感じている方さえいらっしゃいます。
しかも、同居によって住み慣れた地域から引っ越してきたことで、出歩くのも億劫になり、徐々に家に引きこもるようになることもあります。
家族のプライバシーを守り、それぞれが独立した生活を送れるようにすることは大切ですが、完全分離型の二世帯住宅ではない限り、同じ家住んでいるのに顔も合わせないようになって元気を失ってしまうなら意味がないかもしれません。
2. 快適に住み続けるための家づくりのアイディア
いくつになっても快適に暮らしていくためには、家づくりにも工夫が必要です。どのような間取りにすれば良いのか、どんな点を意識すると良いのか、アイディアをご紹介したいと思います。
■外との繋がりを感じられる家
家の中で自由に快適に暮らすことも大事ですが、仕事を退職したり、育児や家事に追われたりすることがなくなり、外に出て人に会うことが減ってしまう高齢者にとって、健康を保っていくためには、家や部屋に引きこもってしまわないように、外との繋がりを感じる工夫が必要です。
2階建てであれば1階に拠点となる部屋を作り、外出しやすい環境にしましょう。部屋から玄関までの動線を短くすることも出来ます。玄関は腰をかけて靴の脱ぎ履きがラクにできるようなベンチを設けることも役立ちます。車椅子になった時や、デイサービスなどで定期的な外出が必要になった時も、玄関までの動線が短いことは助かります。ただし家の中での孤立を防ぐために、リビングや水回りも1階にまとめて家族が顔を合わせ、存在を感じられるようにすることも大切です。
そして、日当たりがよく道路や庭を眺められるような窓を設けることも役立ちます。窓から見える景色で四季を感じたり、公園で散歩している人達が見えたりすると、出かける意欲に繋がります。
■安心して自活できる家づくり
高齢になって体力は低下しても、残存能力を出来るだけ活かしつつ安全に自活した生活を行うためには、生活動線を短くすることが重要です。
特に、転倒リスクを軽減することを意識しましょう。夜に安全にトイレに行けるように寝室とトイレを近くに配置しての動線を短くしましょう。洗面脱衣室を広くとり、家事を行えるようにしたり、その中に洗濯機と部屋干し出来るスペースを設けたりすれば、重たい洗濯物を抱えて移動する必要がなくなります。また、洗濯機がある脱衣室から直接外のベランダに出入り出来るようにしておけば、洗濯物を干すまでの動線も短くてすみます。
さらに、認知機能が衰えていくことを意識して、蛇口の閉め忘れを防ぐセンサー付きの自動水栓に替えたり、コンロの消し忘れを防ぐ、消し忘れ防止機能付きのコンロにしたり、鍵を探す手間が省けるワンタッチでの開閉が可能な玄関ドアを採用したりするなど、トラブルを防ぐために機能付きの設備機器を採用することも役立ちます。
3. まとめ
自分たちが高齢になってきたことや、高齢になった親と共に住むために、高齢者に対応した家へのリフォームを検討している方は少なくありません。快適に暮らすためにバリアフリーにすることを意識する方は多いですが、バリアフリーは段差を無くすことだけではありません。体の残存機能や体力、持病や進行具合を踏まえたうえで何がバリアになっているかを考えて取り除くリフォームを行いましょう。また、家の中や外との孤立を防ぐために、外出しやすく、家族の存在を感じられる間取りにすることも大切です。さらに、動線を短くしたり、認知機能の低下によるトラブルを防ぐための機能付き設備機器を採用したりして、安心して自活した暮らしが出来るようにしましょう。
いくつになっても快適に暮らせる家を目指してリフォームを楽しみましょう!